みなさんは、学級全体に関わることの意思決定としてどのような手段を用いていますか?多分、多くの学級における意思決定方法は「多数決」だと思います。
実際、国会や国連など大きな場でも、多数決は採用されていることを考えると、多数決は我々の意思決定にお馴染みであるとも言えそうです。
多数決のデメリット・反対意見
そんな多数決ですが、「多数決は良くない!」のような論説も存在します。例えば以下のようなデメリット・反対意見があります。
・少数派の意見が無視される
・「数の力」で意見が左右されやすい
・問題の本質を考えずに決まることがある
・「多数派だから正しい」と錯覚する危険
他にも様々あるわけです。個人的は、先日読んだ書籍の以下のセリフが多数決の負の側面を端的を表しているようにも思えるのです。
51対49みたいに、ちょっとの差で決まっても、51の意見が『みんなの意見』になるんでしょ?それって全然みんなじゃなくない?
井出英策:「ふつうに生きるって何?小学生の僕が考えたみんなの幸せ」,毎日新聞出版,2021
多数決のメリット・賛成意見
このような「多数決ってどうなの?」という考え方がある中でも、これだけ多数決が採用されているということは、多数決にもやはり良い面があるはずです。
・1人1票なので、公平でシンプル
・早く決められる
・民主的な方法
・少人数でも大人数でも使える
こうしてみると、現在の民主的な決定システムとしての多数決が採用されていることに少し納得いただけるのではないでしょうか。
多数決の前提
多数決のメリット・デメリット、賛成・反対意見をつらつらと書きましたが、多数決以前に大事なことがあります。それは
多数決の前に「話し合いがしっかりなされた」ということなのだと思います。
多数決のデメリットとして、「少数意見が蔑ろにされやすい」という側面があります。決定したこと=全員の決定、となりがちですが、実は満場一致で決定することはとても少ないです。と考えると少なからず多数決において納得できていない人もいるはずなのです。合意形成後に遺恨を残さないためにも「十分に話し合った上で合意形成を図る」といように仕組まないとならないわけです。理想を言えば多数決で選ばれなかった意見の子も「決定した意見は、自分の意見とは違うけどそれでも良いと思う!」という状態です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
学校はただでさえ忙しく、話し合いをいちいちとれるだけの時間も余力もないですが、教育基本法第1条「教育の目的」にあるように、「民主的な国家の国民」の育成を考えると、この話し合いや合意形成というものをもっと重視すべきだと私は思います。
とりあえず今回の記事で述べたいのは、多数決にはメリットもデメリットもあるということ、そして多数決とセットで話し合いが必要であるということです。
少しでもみなさんの考えの整理になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
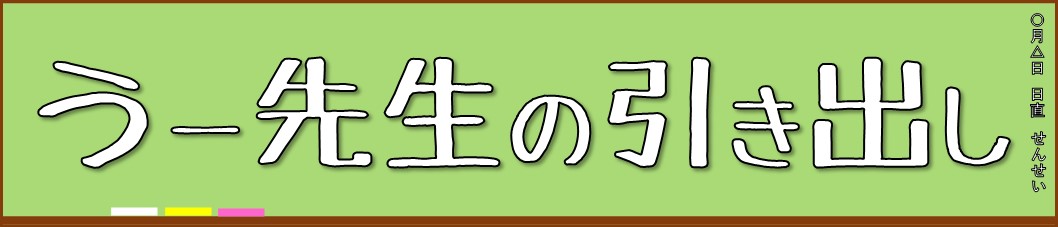



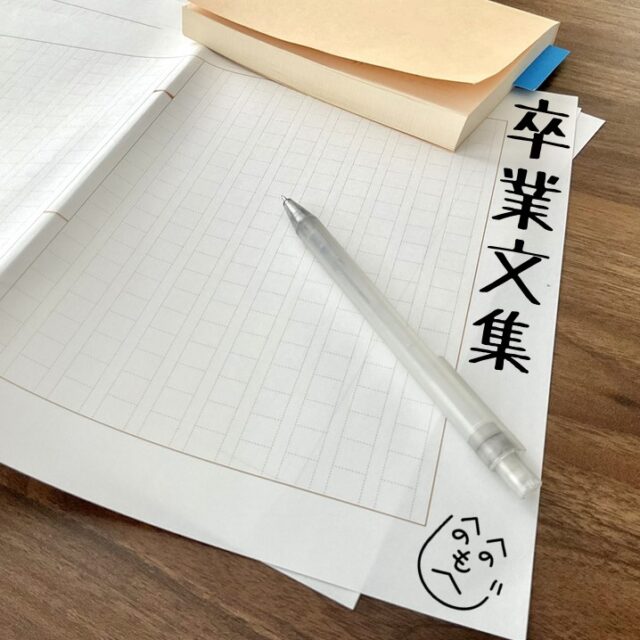




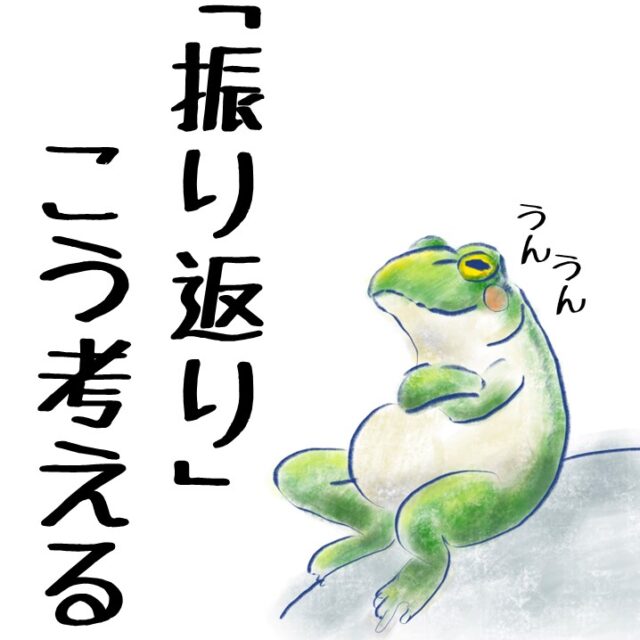



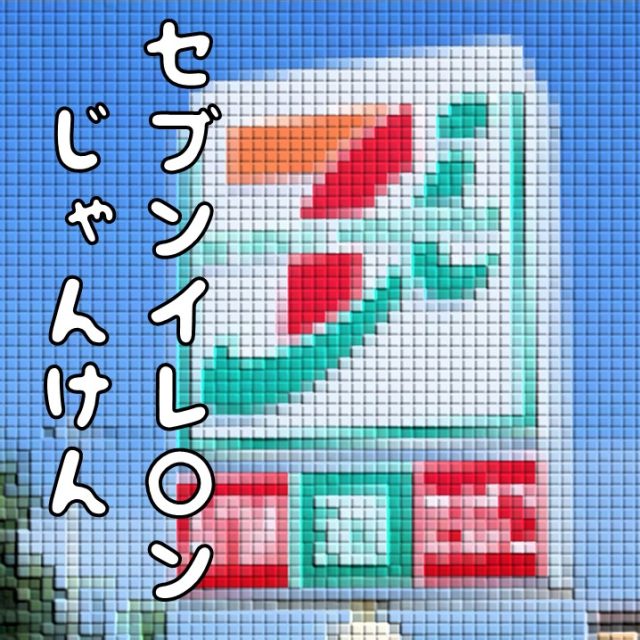
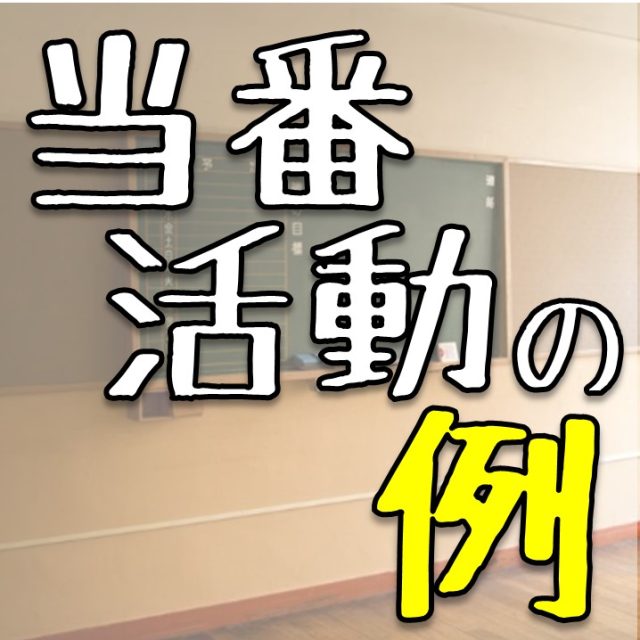

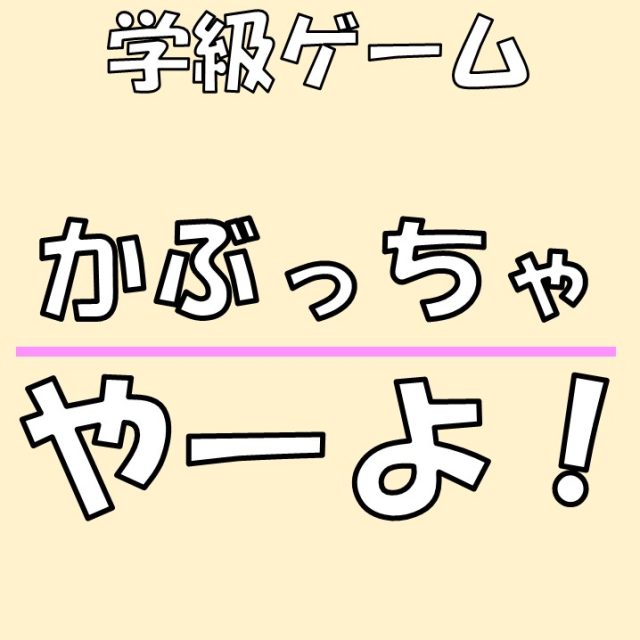
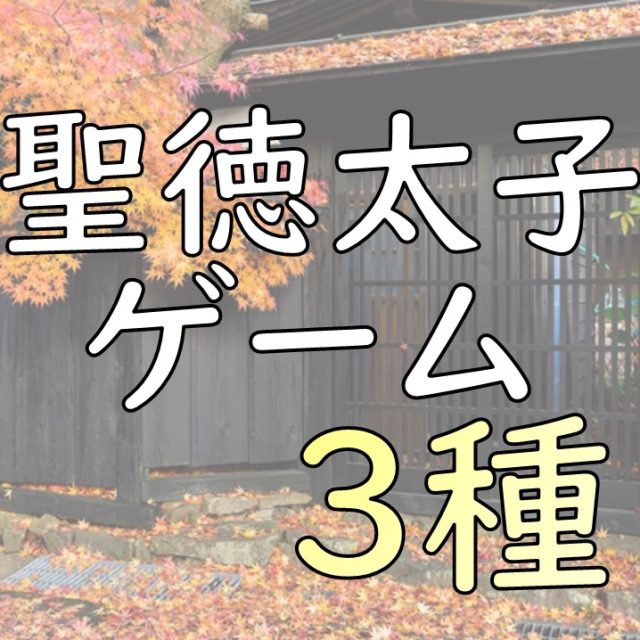


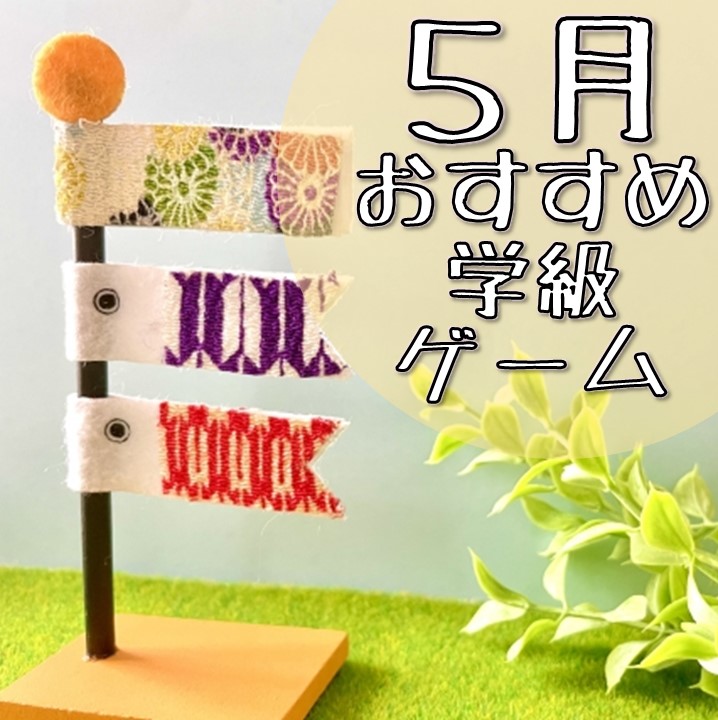
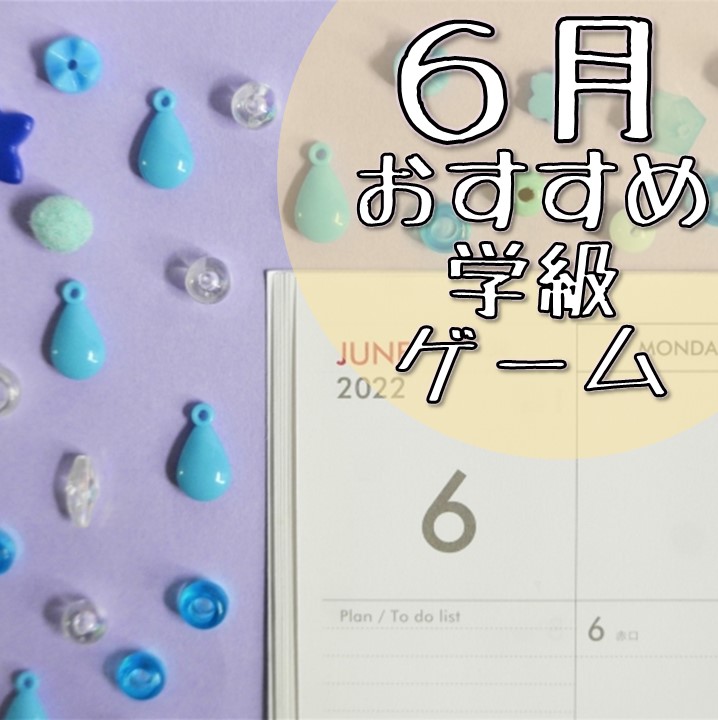
コメント